目的と概要
現場の先生が情報活用能力を育成する授業を行い易くするために、基本となる学習指導要領の体系の整理・提案を行う。また同時に現場の先生方の情報活用能力調査を行い、その結果を盛り込みながら、先生が活用できる体系表、教科別能力表、パッケージ等を作成する。
現場の先生が情報活用能力を育成する授業を行い易くするために、基本となる学習指導要領の体系の整理・提案を行う。また同時に現場の先生方の情報活用能力調査を行い、その結果を盛り込みながら、先生が活用できる体系表、教科別能力表、パッケージ等を作成する。
新学習指導要領に基づく情報教育のあり方を模索する中で、情報活用能力育成調査研究委員会を立上げ、学校現場での実態を調査することにしました。当調査は、学校の情報化の進度や整備状況を捉えようとするものではなく、各教科の先生方がそれぞれの授業をすすめる中で、意識の有無に係わらず、情報活用能力育成についてどの程度の内容を実施しているかの現状を把握しようとするものです。
※アンケートへのご協力、ありがとうございました。
現在、アンケート調査結果を取りまとめ中です。近日中に公開致します。
2019年度は、子どもたちの情報活用能力を育成するためには、どのような授業を行えばよいか、その調査研究を実施し、その成果を当会主催の「第4回関西教育ICT展」のセミナーで模擬授業として行いました。
※現在、資料の公開準備中です。近日中に公開致します。
主体的・対話的で深い学びを実現するためには、コミュニケーション場面において、さまざまな重要なポイントが存在します。例えば、話し合いの目的 何を明らかにし、どういうゴールなのか。または、話し合いの視点 どうすれば話し合いが深まるのか。さらに、話し合いの共有の方法 教師はどのように整理して収束するのかなど、本セミナーでは、タブレット端末などコミュニケーションツールを活用してこのような授業のあり方について、実践イメージが持てる模擬授業と考え方を理解できる講演やパネルディスカッションを行います。
《セミナーテキスト》
「ICTを活用した主体的・対話的で深い学びを実現する授業力育成(コミュニケーション力育成)セミナーのテキストをダウンロードできます。校内研修等で、ぜひご活用ください。
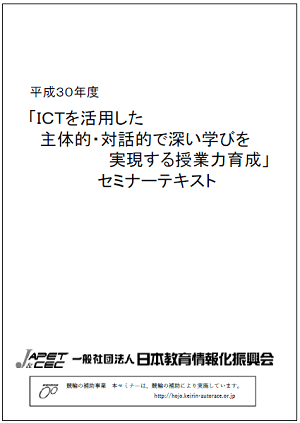
| 日 程: | 平成30年8月2日(木) |
|---|---|
| 会 場: | インテックス大阪(大阪市住之江区南港北1-5-102) |
| 主 催: | 一般社団法人日本教育情報化振興会(JAPET&CEC) 一般財団法人大阪国際経済振興センター、テレビ大阪(株)、 (株)テレビ大阪エクスプロ |
| 後 援: | 文部科学省/総務省/経済産業省近畿経済産業局、大阪府/大阪市 他 |
| プログラム: | (敬称略) |
| 12:00~13:30 | D02 模擬授業 |
| コーディネーター | 柏市立手賀東小学校 校長 佐和 伸明 |
| コメンテーター | 仙台市立六郷小学校 校長 菅原 弘 |
| 模擬授業者 | 金沢市立大徳小学校 教諭 山口 眞希 |
| 15:30~16:30 | D04 総括パネルデイスカッション |
| コーディネーター | 放送大学 教授 中川 一史 |
| パネリスト | 金沢星稜大学 教授 佐藤 幸江 茨城大学 准教授 小林 祐紀 |
| 日 程: | 平成30年12月27日(木) 12:20~16:40 受付:12:00〜 |
|---|---|
| 会 場: | 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属小学校 |
| 主 催: | 一般社団法人日本教育情報化振興会(JAPET&CEC) |
| 共 催: | 日本教育工学協会(JAET) |
| 後 援: | 文部科学省、総務省、経済産業省、金沢市教育委員会、富山県教育委員会、 福井県教育委員会 |
| プログラム: | (敬称略) |
| (1) | 趣旨説明 放送大学 教授 中川 一史 |
| (2) | ポスターセッション |
| (3) | 模擬授業(タブレット端末活用) 中学校3年理科「太陽と恒星の動き」 授業者 鳥取県岩美町立岩美中学校 教諭 岩﨑 有朋 授業指導者 金沢星稜大学 教授 佐藤 幸江 |
| (4) | 総括パネルディスカッション 放送大学 教授 中川 一史 柏市立手賀東小学校 校長 佐和 伸明 仙台市立六郷小学校 校長 菅原 弘一 |
| 日 程: | 平成31年2月16日(土)13:00~16:30 受付:12:30〜 |
|---|---|
| 会 場: | JMSアステールプラザ 4階 大会議室 |
| 主 催: | 日本教育情報化振興会(JAPET&CEC) |
| 共 催: | 日本教育工学協会(JAET) |
| 後 援: | 文部科学省、総務省、経済産業省、広島県教育委員会、広島市教育委員会、 岡山県教育委員会、山口県教育委員会 |
| 協 賛: | 株式会社エルモ社 エルモxSyncカンパニー |
| 参 加: | 定員 60名 |
| プログラム: | (敬称略) |
| (1) | 趣旨説明 放送大学 教授 中川 一史 |
| (2) | 基調講演 「プログラミング教育のこれから」 日本教育情報化振興会 会長 赤堀 侃司 |
| (3) | 模擬授業(タブレット端末活用) 中学校3年理科「太陽と恒星の動き」 授業者 鳥取県岩美町立岩美中学校 教諭 岩﨑 有朋 授業指導者 金沢星稜大学 教授 佐藤 幸江 |
| (4) | 総括パネルディスカッション 放送大学 教授 中川 一史 金沢星稜大学 教授 佐藤 幸江 鳥取県岩美町立岩美中学校 教諭 岩﨑 有朋 |
| 日 程: | 平成31年3月2日(土) 13:00~16:50 受付:12:30〜 |
|---|---|
| 会 場: | 札幌駅前ビジネススペース 2階カンファレンスルーム |
| 主 催: | 日本教育情報化振興会(JAPET&CEC) |
| 共 催: | 日本教育工学協会(JAET) |
| 後 援: | 北海道教育委員会/札幌市教育委員会 |
| 定 員: | 80名 |
| プログラム: | (敬称略) |
| (1) | 趣旨説明 放送大学 教授 中川 一史 本セミナーのポイントについて、ご説明いただきます。 |
| (2) | 基調講演 「プログラミング教育のこれから(仮題)」 (一社)日本教育情報化振興会 会長 赤堀 侃司 |
| (3) | 模擬授業(タブレット端末活用) ①小学校6年算数「きみたちはコインパーキングのオーナーになれるか」 金沢星稜大学 教授 佐藤 幸江 ②小学校5年社会「情報社会を生き抜くための3箇条をまとめよう」 茨城大学 准教授 小林祐紀 |
| (4) | 総括パネル 模擬授業のポイント等をわかりやすく解説し、セミナー内容を総括的にまとめていきます。 放送大学 教授 中川 一史 金沢星稜大学 教授 佐藤 幸江 千葉県総合教育センター 所長 秋元 大輔 茨城大学 准教授 小林 祐紀 |
今までの学習指導要領では、学習内容(「何を学ぶのか」)が書かれているのが中心でした、ここに、「何ができるようになるのか」と「どのように学ぶか」が加わりました。 今まで書かれていた学習内容、つまりここでいう「何を学ぶか」だけでなく、育成したい力、育成したい子供像としての「何ができるようになるのか」、そして、そのような子供たちをどのように育てていくかという「主体的・対話的で深い学び」いわゆる「アクティブ・ ラーニング」という「どのように学ぶのか」という3つがあげられています。
3つの学びについては、それぞれこのようになっております。この中で、対話的な学びについて掘り下げましょう。「アクティブ・ラーニングは、「深い学び」「対話的な学び」「主体的な学び」の三つの学びに置き換えられています。学習者がどれだけ考えるようになったか、どう対話するようになったか、どう主体的に学ぶようになったのかといったように学びに向かう子どもの変化を期待しているのです。
| 日 程: | 平成29年5月27日(土) 13:00~16:40 受付:12:30〜 |
|---|---|
| 会 場: | 新潟大学駅南キャンパス ときめいと |
| 主 催: | 日本教育情報化振興会(JAPET&CEC) |
| 共 催: | 日本教育工学協会(JAET) |
| 後 援: | 文部科学省/総務省/経済産業省、新潟県教育委員会/新潟市教育委員会 機材・ソフト協力:NTT東日本(株)、パイオニアVC(株) |
| 定 員: | 100名 |
| プログラム: | (敬称略) |
| (1) | 趣旨説明 放送大学 教授 中川 一史 |
| (2) | 基調講演 「主体的・対話的で深い学びを支えるリテラシー」 新潟大学 准教授 後藤 康志 |
| (3) | 模擬授業 「アクティブ・ラーニングでのタブレット端末等の活用」 ①小学校5年社会「食料生産の未来を考えよう 」 金沢市立大徳小学校 教諭 山口 眞希 ②中学校3年理科「地球と宇宙」 鳥取県岩美町立岩美中学校 教諭 岩﨑 有朋 |
| (4) | 総括パネル 放送大学 教授 中川 一史 金沢星稜大学 教授 佐藤 幸江 鹿児島大学大学院 准教授 山本 朋弘 |
| 日 程: | 平成29年7月1日(土) 13:00~16:40(予定) |
|---|---|
| 会 場: | 栃木県総合文化センター |
| 主 催: | 日本教育情報化振興会(JAPET&CEC) |
| 共 催: | 日本教育工学協会(JAET) |
| 後 援: | 文部科学省/総務省/経済産業省、栃木県教育委員会/宇都宮市教育委員会/大田原市教育委員会 機材・ソフト協力:NTT東日本(株)、パイオニアVC(株) |
| 定 員: | 100名 |
| プログラム: | (敬称略) |
| (1) | 趣旨説明 放送大学 教授 中川 一史 |
| (2) | 基調講演 「2020年代に向けた教育の情報化について」 文部科学省生涯学習政策局情報教育課情報教育振興室 室長補佐 稲葉 敦 |
| (3) | 模擬授業 「アクティブ・ラーニングでのタブレット端末等の活用」 ①小学校6年社会「平和で豊かな暮らしを目指して 」 熊本県八代市立八代小学校 教諭 樋口 勇輝 ②中学校3年理科「地球と宇宙」 鳥取県岩美町立岩美中学校 教諭 岩﨑 有朋 |
| (4) | 総括パネル 「主体的・対話的で深い学びとコミュニケーションツールの活用」 放送大学 教授 中川 一史 金沢星稜大学 教授 佐藤 幸江 鹿児島大学大学院 准教授 山本 朋弘 |
| 日 程: | 平成29年9月2日(土) 12:50~16:55(予定) |
|---|---|
| 会 場: | 鹿児島大学教育学部講義棟(郡元キャンパス) |
| 主 催: | 日本教育情報化振興会(JAPET&CEC) |
| 共 催: | 日本教育工学協会(JAET) |
| 後 援: | 鹿児島教育委員会/熊本県教育委員会/宮崎県教育委員会/福岡県教育委員会/佐賀県教育委員会、 長崎県教育委員会/大分県教育委員会/鹿児島市教育委員会 |
| 機材協力: | 富士電機ITソリューション(株)/リコージャパン(株) |
| 定 員: | 200名 |
| プログラム: | (敬称略) |
| (1) | 趣旨説明 放送大学 教授 中川 一史 |
| (2) | 基調講演 「プログラミング教育の現状と今後の展開」 日本教育情報化振興会 会長 赤堀 侃司 |
| (3) | 模擬授業 「アクティブ・ラーニングでのタブレット端末等の活用」 ①小学校6年国語「町のよさを伝えるパンフレットを作ろう 」 佐賀市教育委員会 指導主事 横地 千恵子 ②小学校6年社会「平和で豊かな暮らしを目指して」 熊本県八代市立八代小学校 教諭 樋口 勇輝 |
| (4) | 総括パネル 「主体的・対話的で深い学びとコミュニケーションツールの活用」 放送大学 教授 中川 一史 金沢星稜大学 教授 佐藤 幸江 鹿児島大学大学院 准教授 山本 朋弘 |
| 日 程: | 平成30年2月17日(土) 13:00~16:40(予定) 受付:12:30〜 |
|---|---|
| 会 場: | 沖縄産業支援センター 1階大ホール |
| 主 催: | 日本教育情報化振興会(JAPET&CEC) |
| 共 催: | 日本教育工学協会(JAET) |
| 後 援(予定): | 沖縄県教育委員会/那覇市教育委員会 |
| 参加費: | 無料 |
| 定 員: | 80名 |
| プログラム: | (敬称略) |
| (1) | 趣旨説明 放送大学 教授 中川 一史 本セミナーのポイントについて、ご説明いただきます。 |
| (2) | 基調講演 「教育改革を踏まえた教育の情報化の重要性」 文部科学省 生涯学習政策局 情報教育課 情報教育振興室長 安彦 広斉様 |
| (3) | 模擬授業(タブレット端末活用) ①小学校5年社会「食料生産の未来を考えよう」 金沢市立大徳小学校 教諭 山口 眞希 ②小学校6年国語「町のよさを伝えるパンフレットを作ろう」 佐賀市教育委員会 指導主事 横地 千恵子 |
| (4) | 総括パネル 「主体的・対話的で深い学びとコミュニケーションツールの活用」 放送大学 教授 中川 一史 金沢星稜大学 教授 佐藤 幸江 鹿児島大学大学院 准教授 山本 朋弘 |
1.セミナー開催
本事業で提供するセミナーは、全国の小中学校が掲げている研究テーマの一プログラムとして実施される場合が多くなっているため、教員が比較的時間を確保し易い、土曜日や学校の休み期間に開催しています。
以下、セミナー参加者の所感の抜粋です。
1)子供たちが主体的に授業に参加できる方法として、効果的だと思った。
2)ジグソー学習/パネルディスカッションでの先生方の取るべき姿が見れて、参考になった。
3) 主体的・対話的な学びから、自分の思考が深化していく学習過程のモデルを提案していただいたことで、どの教科でも応用することがと強く感じた。ICTの活用がすごいのではなく、授業設計がすごいと感じた。
4)タブレットを持つことで、「発表したい」「伝えたい」意欲は高まると思うので、国語や総合のプレゼンの場面で活かせると思う。
5)総合的な学習で、本校の特色や町の特産物などをPRするような内容を考えている。是非、ICTをツールとした授業をすすめコミュニケーション力を育成し、地域とつながっていきたい。
| 日 程: | 平成28年10月29日(土) 13:00~16:30 |
|---|---|
| 会 場: | 福岡市 リファレンス博多駅東 5階 V-1会議室 |
| 主 催: | 日本教育情報化振興会(JAPET&CEC) |
| 共 催: | 日本教育工学協会(JAET) |
| 後 援: | 文部科学省/総務省/経済産業省、福岡県教育委員会/福岡市教育委員会/佐賀県教育委員会/ 熊本県教育委員会/鹿児島県教育委員会 |
| 定 員: | 100名 |
| プログラム: | (敬称略) |
| (1) | 趣旨説明 放送大学 教授 中川 一史 |
| (2) | 基調講演「これからの学びとコミュニケーション能力」 (一社)日本教育情報化振興会 会長 赤堀 侃司 |
| (3) | 模擬授業 「アクティブ・ラーニングでのタブレット端末等の活用」 ①6年国語 「町の良さを伝えるパンフレットを作ろう」 佐賀県みやき町立中原小学校 教諭 横地千恵子 熊本県八代市立八代小学校 教諭 樋口 勇輝 ②5年総合的な学習の時間 「ストップ地球温暖化」 板橋区立上板橋第四小学校 教務主幹 浅井 勝 |
| (4) | 総括パネル 「主体的・対話的で深い学びとコミュニケーションツールの活用」 放送大学 教授 中川 一史 金沢星稜大学 教授 佐藤 幸江 鹿児島大学教育学部 講師 山本 朋弘 |
| 日 程: | 平成29年2月18日(土) 13:00~16:30 |
|---|---|
| 会 場: | 仙台市情報・産業プラザ(ネ!ットU)6階 セミナールーム |
| 主 催: | 日本教育情報化振興会(JAPET&CEC) |
| 共 催: | 日本教育工学協会(JAET) |
| 後 援: | 文部科学省/総務省/経済産業省/宮城県教育委員会/仙台市教育委員会/福島県教育委員会/ 山形県教育委員会 |
| 定 員: | 100名 |
| プログラム: | (敬称略) |
| (1) | 趣旨説明・基調講演 「主体的・対話的な深い学びとコミュニケーションツールの活用」 放送大学 教授 中川 一史 |
| (2) | 模擬授業 「アクティブ・ラーニングでのタブレット端末等の活用」 ①5年社会「これからの食料生産とわたしたち 」 仙台市立錦ヶ丘小学校 教諭 石井 里枝 ②4~6年総合的な学習の時間「まちの魅力を伝えよう」 金沢市立大徳小学校 教諭 山口 眞希 |
| (3) | 総括パネル 「主体的・対話的で深い学びとコミュニケーションツールの活用」 金沢星稜大学 教授 佐藤 幸江 鹿児島大学教育学部 講師 山本 朋弘 仙台市立六郷小学校 校長 菅原 弘一 |
2.学習教材開発
平成22年度から平成27年までの5年間を通じてコミュニケーション力を育成するための授業例を中心としてまとめた教材(研修モジュール)を開発しました。今回は、学校や地域での研修会で実施したりしてきた21世紀型コミュニケーションを育成するツールとしてのタブレット端末、ホワイトボード、思考ツールのマッピングをもとに、その活用効果や授業での活用における留意点について深めていきました。開発した教材(研修モジュール)は、以下の構成となっています。
学習教材(研修モジュール)の内容
| タイトル | 構成 |
|---|---|
| A ブレーンストーミング・KJ法 モジュール | 参加型の学習方法である「ブレーンストーミング」及び「KJ法」を体験するワークショップ |
| B イメージマップ モジュール | イメージマップの基本から応用までを体験するワークショップ |
| C ホワイトボード モジュール | 21世紀型コミュニケーション力とは何かを理解し、ホワイトボードの特性を体験するワークショップ |
| D タブレット端末 モジュール | タブレット端末のツールとしての特徴を理解し、その活用バリエーションの充実を目指す |
「ICT社会におけるコミュニケーション力の育成」指導のポイントをテーマとしてセミナーを開催しました。
| 日 程: | 福岡市 リファレンス博多駅東 5階 V-1会議室 |
|---|---|
| 会 場: | 仙台市情報・産業プラザ(ネ!ットU)6階 セミナールーム |
| 主 催: | 日本教育情報化振興会(JAPET&CEC) |
| 共 催: | 日本教育工学協会(JAET) |
| 後 援: | 文部科学省/総務省/経済産業省 福岡県教育委員会/福岡市教育委員会 佐賀県教育委員会/熊本県教育委員会 鹿児島県教育委員会 |
| 定 員: | 100名 |
| プログラム: | (敬称略) |
| (1) | 基調講演 「ICT社会で学び合う子どもたちと協働学習」 日本教育情報化振興会 会長 赤堀 侃司 |
| (2) | パネル討論(趣旨説明) 放送大学 教授 中川 一史 金沢星稜大学 教授 佐藤 幸江 鹿児島大学教育学部 講師 山本 朋弘 |
| (3) | 模擬授業・ワークショップ タブレット端末・思考表現ツールを活用した協働学習 ①小学校コース 熊本県山江村立山田小学校 教諭 樋口 勇輝 ②中学校コース 鳥取県岩美町立岩美中学校 教諭 岩崎 有朋 |